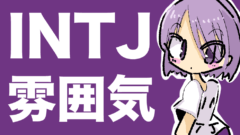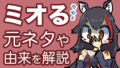こんにちは、つむぎゆりです!
今回は、方言である「いなげな」の語源や由来を解説します。
結論からいうと、「いなげな」は『変な、奇妙な』という意味で広島や愛媛で使われています(語源は不明)。
「~げな」は『~らしい』『~なんて』という意味で、九州や中部で使われており、語源は「げ」と「なり」が合わさったことが由来です(記事内で詳しく解説)。
いけずの語源↓
ぬくとい・ぬくいの分布↓
首都圏の方言まとめ↓
「いなげな」について調査
方言大辞典(刊:あかね書房)によれば、「いなげな」は広島や愛媛の方言で、意味は「変な、いやな」とされています。
全国方言辞典(刊:三省堂)を見ても、愛媛県の方言として紹介されており、意味は「奇妙な、嫌な」とありました。
というわけでこの記事は終わり…いえいえ終わりません笑
どこのサイトにでもあるような前置き情報はここまでにして、本題に入っていきますw
「いな+げな」で「いなげな?」
なぜこの記事を書こうと思ったかというと、きっかけはアクセス解析からでした。
アクセス解析で「いなげな」できてくれた方がいて、これは方言だろうなと思って辞書を調べたら、案の定正解。
そこまでは普通だったのですが、「中国・四国の方言」(刊:ゆまに書房)を見たら、以下のような記載があったんですよね。
香川の人は「~げな、げに(げん)」を使います
…ということは、ひょっとしたら、「いな」が「嫌」という意味で、「げな」が「でな、でさ」といった意味なのではと思い、これは語源や由来を調べたらおもしろそうだぞ、と思って執筆にいたります笑
「中国・四国の方言」の抜粋
以下、上記の「中国・四国の方言」の書籍内容を抜粋すると以下のとおり。
「おせげんなったのぉ」(大人っぽくなったなぁ)
「うまげな服きとるでないか」(良さそうな服を着ているじゃない)
「うれしげんしとったらおっかれるぞ」(えらそうに調子にのっていると叱られるよ)
2003年に発行された本ですが、書籍を見ると「~げ」「~げん」も使われていることがわかります。
なるほど、「げな」の方言を調べないと、本当の意味で「いなげな」の意味もわからないような気がしてきました笑
「いなげな」の補足
というわけで、「げな」について調べるまえに、「いなげな」について補足しておきます。
辞書を引いた情報はもう終了なのですが、ネットを見るかぎり、「いなげな」はもうあまり使われていないようで、ご年配の方でなければ日常会話で意味が通じない可能性が高いのだとか。
ちなみに、「いなげな 方言」で検索すると、スーパーの「いなげや」がヒットしたのですが笑、まったく「いなげな」と関係なく、スーパーのいなげやの由来は「創業者が生まれた地域を治めていた豪族の稲毛三郎重成が由来」とのこと。
「げな」の意味や使い方を調査
というわけで後半では、「~げな」について調べていきたいと思います。
軽く調べたところ、かなり広範囲にわたりいろいろな使い方がされているようで、これは骨が折れそうな作業な予感がしました笑
全国方言辞典を調べてみる
全国方言辞典によれば、「~げな」の意味や分布は2種類の記載があり、以下のとおりとなります
「~げな」
- 主に使われる地域:福岡県の西部(福岡市、宗像市、糟屋部など)と南部(久留米市、柳川市、大牟田市、八女郡)
- 意味は「伝聞」や「例示」
【例文】
- 「あのひたー、ごーかくしたげな」(あの人は合格したそうだ)
- 「なんでがっこーげな、いかんといかんとねー」(どうして学校なんて行かないといけないの?)
上記を見ると、文末に語尾のようにつける使い方、そして文中に言葉のつなぎとしても使えるっぽいですよね。
つづいて、宮崎県でも「げな」(~げなではない)での記載がありました。
「げな」
- 地域:宮崎県
- 意味:~そうだ
【例文】
「げなげなばなしはうそじゃげな」(~らしいよって話は、嘘だということだ)
えーと、例文が高度すぎてよくわからないのですが笑、要は不確定なときに使うって意味合いでいいような気がします(たぶん)。
ネットでの調査
これがですね、とにかくいろいろな地域で、さまざまな使い方がされておりまして笑
とりあえず主要なものを可能なかぎりピックアップしたいと思います。
「げな」の使われている地域と意味
- 鳥取弁:助動詞として
- 福岡弁:伝聞、例示
- 熊本弁:~らしい、~そうだ
で、調べていくうちに、コトバンクのページがめちゃめちゃ詳しく、もう調べる必要はないんじゃないかくらい内容が詰め込まれていました笑
ただ文章が堅くわかりづらいと思われるので笑、コトバンクの内容をかみくだくと以下のような感じかなと。
- 活用は「げに」「げで」「げなれ」
- 気配を表す「げ」に、断定の助動詞である「なり」がついたもの
- 意味は「伝聞」や「推測」
- 狂言でも使われていた(室町時代末期~近世初期)
- 室町時代からは「推測」の意味で使われていたが、近世になって「伝聞」の意味に転じてきた
- しかし江戸後期に「そうな」が流行り、衰退していった
今までのまとめ
方言「~げな」まとめ
意味:「らしい、だそうだ」のように推測や伝聞で使う
語源:「げ(気配)」に、助動詞の「~なり」がついたことから
由来:室町時代から近世初期まで使われていたが、現在では衰退気味となっている
分布:九州・中国・四国などを中心に広まっている
というわけで、「~げな」の語源や由来は、コトバンク(コトバンクも精選版日本国語大辞典が出典だが)で、ほぼわかってしまった感じです笑
ただ、調べていくと「~げな」に関して、もうひとつだけ興味深い情報がありました。
2009年に「げな」を新方言として研究した論文
なんと、2009年に新方言として「げな」を研究した論文を発見しました笑
ちなみにこの論文は脚注を除くと16Pあるのですが、ここまできたらこれを読んで、その内容を抜粋してお届けしたいと思います笑
論文の要点を抜粋
より正確な情報は論文のPDFを見ていただくとして、ここでは簡潔に要点をまとめてみたいと思います。
- 2007年ごろに福岡でおこなわれた調査をもとに、2009年に発表された論文
- 「そこの家で赤ん坊が生まれたげな」のような、「伝聞」は福岡市では衰退気味
- 「こげな所げな聞いとらんばい!」(こんなところなんて聞いてないよ!)のような、伝聞以外の「げな」が最近若者のあいだで広まってきた
- ほぼ福岡県内限定で使われていて、18~25歳の若年層が主に使用
- 最近の「げな」のニュアンスは、否定的ニュアンスに使われることが多い(※要は、文の途中で「~なんて」のような感じで「げな」が使われている)
- 上記の使い方は共通語でいうと、「とか」「なんて」「なんて」に該当する
- この新しい「げな」は、主に福岡方言話者が使っている
- 「そげなこと言うな」のそげなと、伝聞の「げな」が混ざった可能性がある
まず注意点としては、2007年の若年層が使っていたと論文内にあるのですが、この記事執筆時点(2022年)からするとタイムラグがある点ですよね。
で、それを留意したうえで論文の要点をまとめると、2007年の調査で若者のあいだでは「~なんか」「~なんて」のような用法で「げな」が福岡県で使われていた、といった内容が要点だと思われます。
総じて「いないげ」や「げな」のまとめ
というわけで、この記事のまとめと結論です。
「いないげ」の意味は「変な、奇妙な」で、広島や愛媛で使われている
「げな」は「~らしい、~そうだ」のように推測や伝聞の意味で、語源は「げ」と「なり」が合わさったもので、九州・中国・四国などで使われている
最近になって「げな」は、「~なんて」「~なんか」のように、否定的な比較の使い方として、文中に使われ始めた
ちなみに、「いないげ」についての語源は結局のところわかりませんでした笑
僕が思うに、「否」や「嫌」が転じたもので、そんなに複雑な理由ではなさそうな印象でしたが、どの書籍やサイトにも載っていないので今のところ真相はわからずじまいですねw
…いやーなるほど、いないげの意味などはサイトを少し調べただけで出てきましたが、「げな」がなかなか強敵でした笑
とくに、論文はかなり面白くて、方言などに興味がある方はぜひ読んでみることをおすすめします(だいぶ記事では内容も端折ってますし)。
ちなみに、従来の「げな」が衰退しつつあることと、新しい「げな」の使い方が若年層を中心に広がったことも、なんだか偶然じゃない気も僕はしました。
つまり、昔の意味を若年層が知らなかったからこそ、「そげなこと~」のようなメジャーな方言の意味が、使いやすいかたちで文中に使われれるようになったのではないでしょうか。
まとめ
以上、いなげなの語源や由来を解説しました!
予想以上に調べることがあって、半日かかりましたが笑、言葉の変遷の理由を知ることができて非常に楽しかった次第です。